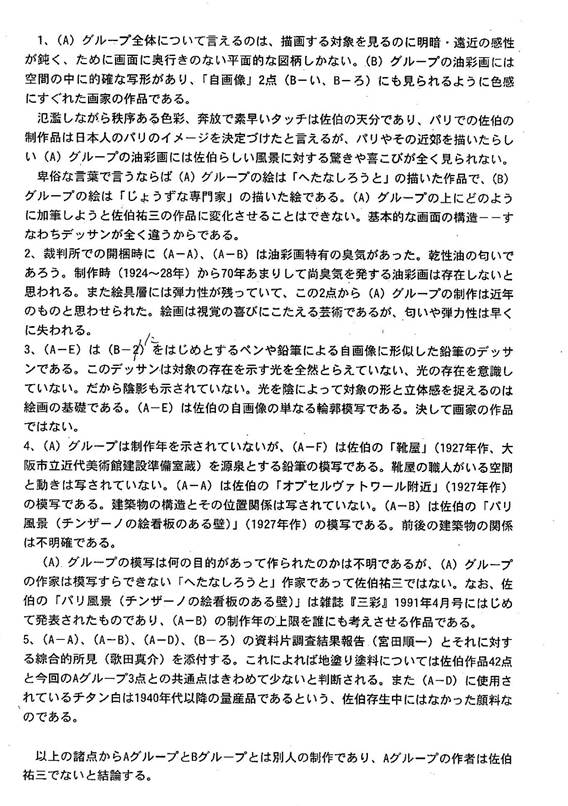第二部 青木茂鑑定の虚妄 弁護士中鉢秀一準備書面
第一部で触れましたが、中島事件の原告側弁護士が提出した準備書面の一部をここに御紹介します。中島事件は平成8年8月13日に提訴され、平成8年(ワ)第15761号事件と呼ばれるようになりました。その裁判において原告代理人中鉢秀一氏が提出されました準備書面の一部を以下に掲載いたします。
一部に、見易いように色を変えた部分、太字にした部分があります。また、読者諸兄のイメージが混乱しないように、裁判で用いられた記号に替えて絵画のすべてに具体的な品名を付し、またA・B・Cの作品グループを内容に応じて、「吉薗グループ」「若描きグループ」「加筆グループ」と呼ぶことにいたしました。
また、「青木茂鑑定書」をそのまま、この部の末尾に掲載しました。
Ⅰ・平成10年12月21日付準備書面(提訴後2年4ヵ月経過)
一・迷走の感を深めている本件訴訟であるが、もともと単純な事案ではないだろうか。
骨董ブームあるいは骨董鑑定ブームを背景として『骨董の真贋』を執筆した被告中島が、「ものを買うときは、耳で買わない、目で買え」と説いている一文の中で、吉薗コレクションを贋作と決めつけた。
同コレクションの真贋については、新聞・雑誌で度々報じられ、その上同人は贋作と断じた東美の会員でもある立場上、真贋を判断するのに吉薗資料が重要であること、その資料の中で佐伯夫人米子が自己の加筆等を認めていることも知っていたと思われる。
被告中島には、洋画の鑑定というのは畑違いのことであり、しかも実物を見もしないで贋作としたのである。一文には「自分自身の怜悧な目でもって、そのものをみるべきなのです」とある。皮肉なことである。
訴訟提起前の原被告間の交渉のなかで、被告中島は実物を直接見ていると明言していたが、被告本人尋問では「芸術新潮」平成8年4月号に掲載された写真で見た
と後退、(同尋問で同人は『骨董の真贋』の原稿を最終的に完成したのは、平成8年2月の終わりか、3月初旬と答えている。一方、「芸術新潮」平成8年4月号が発売されたのが平成8年3月25日である。とすれば、被告は原稿を最終的に完成した時点で写真を見ていないことになるが)その写真で、贋作であることがわかったと述べている。その理由を余りの稚拙さに求めている。
しかし、吉薗コレクションの真贋論争のなかで夫人米子の加筆の事実の有無の占める重要性を考えれば、稚拙さが贋作と判断する根拠にはなりにくいような気がする。
(本ものが微動だにしない一般の真贋騒ぎと本件との相違がこの点にある)。
被告中島は畑違いの分野である吉薗コレクションを鑑定はおろか実物を見もせずに贋作ときめつけ、一文中にはそれを納得させる理由を何ら示していない。いわゆる床屋談義を本にしてしまったのである。鑑定人を標榜する者として許されないことである。被告㈱二見書房は、一文の内容を了解して出版発行したのであるからこれ又許されない行為である。
二・被告側は平成9月26日付準備書面第4項にて、原告には損害がないという。
一文発表前の各種マスコミの報道により、原告の社会的評価が極度に低下していたから、一文の発表で更に低下することはないとの理由である。
一文に先行する各種マスコミの報道は、程度の差こそあれ、原告に有利な事実も不利な事実も伝えている。このような報道では、社会的評価は固まらず、まして極度に低下した事実はない。
仮に、社会的評価が先行報道により多少低下したことがあったにしても、被告らの一文発行により、原告に被害が生じないというのは乱暴な言である。理由も示さずに、(遠野あたりに佐伯作品が大量にあるわけはないという一文中の記載は理由には到底成りえないものである)贋作呼ばわりした被告らの行為により、原告の社会的評価は著しく低下したのであり、現に、前回の準備書面で触れたような投石騒ぎすら起きている。
被告の論は、負傷者に暴行を加えても新たな暴行罪・傷害罪は成立しないと言うに等しい。
三・被告より鑑定の申請がなされているが、本訴訟の目的は吉薗コレクションの真贋を判定することではない。理由・根拠を示すことなく同コレクションを贋作として本を発行した被告らの行為が名誉毀損に該るか否かを判断するのに、真贋の鑑定が不可欠のこととは思えない。被告は、米子の介在する可能性が皆無の佐伯作品と吉薗コレクションが異質であることを証するために本申請をするとしているが、米子が手を加えた可能性が皆無の作品を見つけ出すことの困難さ、佐伯自身の作風の変化等を考えると鑑定の結果に多くを期待できない。
その上、被告が推薦している人物が本件真贋論争ですでに態度を表明していることは、証拠上も窺うことができ、いかがなものであろうか。(末尾略)
Ⅱ・平成14年5月21日付準備書面(提訴後5年9ヵ月経過)
第1 本件鑑定の目的
本件鑑定は「佐伯が単独で描いたことが明らかな初期作品と吉薗コレクションの異 同を調べるために行われた。
鑑定の方法は、油彩画・デッサンともに肉眼にて行うが、鑑定人の申し出により、顔料及び地塗りの分析検査も行われることになり、宮田順一氏が鑑定補助者としてその任にあたることとなった。
第2 本件鑑定の実際
平成13年10月30日付で青木茂鑑定人の鑑定書が提出された。
鑑定書には鑑定補助者宮田順一作成の資料片調査結果報告書が付されているが、更に歌田眞介作成の『宮田順一「調査結果報告」についての綜合的所見』なる一文も付されている。
歌田氏の本件裁判に於ける身分はどのようなものであろうか、鑑定人に選任されたことはない。鑑定補助者であろうか? 被告代理人は平成14年2月26日付準備書面中で歌田鑑定補助者と言う表現を用いており、同氏が鑑定補助者であることを自明のこととしているようである。しかし果してそうであろうか?
平成12年3月25日付書面にて青木鑑定人が顔料及び地塗りの分析検査を行いたいとの申し出をなし、その結果宮田氏が鑑定補助者に選ばれたことは先に述べた。(同じ書面で青木鑑定人は分析検査の効果が限定的であるとも言っている。)
宮田氏が鑑定補助者となったのは、そのような必要があったからであり、歌田氏にはどのような必要があるのであろうか。
鑑定人はその責任において履行補助者を使用することはできようが、履行補助者のなしうることは文字通りの単純作業程度のものに限られる。もし歌田氏を青木鑑定人が独自の判断で鑑定補助者としたのであれば、そのうえ体裁・内容とも堂々の 綜合的所見の作成を依頼したのであれば、決して許されることではない。
原告代理人は本件鑑定書から歌田文書を削ることを求める。
第3 本件鑑定の枠
本件鑑定の対象から米子加筆の可能性のあるものは省かれている(それがために被告側は大変なご苦労をしている。)
米子加筆のおそれのあるものにはふれないことを鑑定人は熟知していた筈である。鑑定人が鑑定補助者の補助を受けるときは、自己に課せられた制約を鑑定補助者にも等しく守らせなければならない。
宮田報告書中、3「調査結果の比較」のなかで、さりげなく創形美術学校修復研究所が先になした佐伯作品42点の地塗層の分析結果と比較している。これは約束違反であり、鑑定人の失体である。「調査結果の比較」のうち該当部分は削除されなければいけない。
第4 本件鑑定の結論と理由
本件鑑定書は宮田報告書が作られた後、11ヶ月余経過してから作成されている。いかなる理由でかくも遅延したのか甚だ奇異であるが、鑑定人はAグループ(「吉薗グループ」)とBグループ(「若描きグループ」)のそれぞれの作者は全くの別人で「吉薗グループ」の作家は佐伯祐三ではありえない、と結論づけ、
その理由として、
(1) 要するに下手だから佐伯ではない
(2) 油彩画特有の匂いがしたし、絵具は弾力性があるから近年の創作である。
(3) 「吉薗グループ」の一部の作品に使われているチタニウム・ホワイト(ルチル型)は佐伯死後(1940年代)の産物である。
以上の3点を挙げる。
第5 理由(1)に対する反論
鑑定書理由のうち1・3・4がこれに該当する。
1 鑑定書理由1(注・青木鑑定書が挙げた理由1のこと)
「吉薗グループ」全体について言えるのは、描画する対象を見るのに明暗・遠近の感性が鈍く、ために画面に奥行きのない平面的な図柄しかない。「若描きグループ」の油彩画には空間の中に的確な射形があり、「自画像」2点(「芸大自画像」、「笠間自画像」)にも見られるように色感にすぐれた画家の作品である。
氾濫しながら秩序ある色彩、奔放で素早いタッチは佐伯の天分であり、パリでの佐伯の制作品は日本人のパリのイメージを決定づけたと言えるが、パリやその近郊を描いたらしい「吉薗グループ」の油彩画には佐伯らしい風景に対する驚きや喜びが全くみられない。
「吉薗グループ」の絵は「へたなしろうと」の描いた作品で、「若描きグループ」の絵は「じょうずな専門家」の描いた絵である。
「吉薗グループ」の上にどのように加筆しようと佐伯の作品に変化させることはできない。基本的な画面の構造――すなわちデッサンが全く違うからである。


左
芸大自画像
右
笠間自画像
[反論]
鑑定人の論旨は3段に分かれる。第一段で言うところの差異は結局、「色彩」と「遠近感」に尽きる。ただし、「感性が鈍く」「的確な射形」「色感にすぐれた」等は、単なる印象と主観的判断にすぎず、具体的に説明していないから反論のしようもなく、またする必要もないと思われる。また、言うところの「奥行きのない平面的な図柄」については、たしかにそのように見えるが、これには下記の明白な理由がある。
第2段では「氾濫しながら秩序ある色彩、奔放で素早いタッチ」を佐伯の天分と断定し、「吉薗グループ」はそれに該当しないと言いたいようであるが、その理由が明確でない。また、佐伯の天分が「氾濫しながら・・・・」にあるとしても、終生それに限定されていたとの論証はどこにもなく、言及すらない。さらに、「佐伯らしい風景に対する驚きや喜び云々」に至っては、鑑定人自身の主観の感覚的表現にすぎず、反論のしようがないこと前述の通りである。
第3段では、「吉薗グループ」の作品を「へたなしろうと」とし、「若描きグループ」の作者を「じょうずな専門家」と断定するが。「へた」と「じょうず」の概念につき、何の説明もない。そもそも遠近感や色彩において、目視感覚や写真に近いものを一義的に「じょうず」とし、それから離れるほど「へた」とするのは俗流の見解であり、否々今日、俗流ですらまれな見解である。仮に「じょうず」「へた」についてそのような表現が許されるとしても、「じょうず」と「専門家」、「へた」と「しろうと」を一義的に結び付けることはありえない。
例えば佐伯も交流のあった熊谷守一は、画歴を重ねた結果、極めて輪郭単純にして陰影のない画風を確立した。
佐伯と同年配の東郷青児がたどり着いたのは、遠近感や陰影のまったくない表現法である。
鑑定人の言う「じょうず」が大昔の俗流的絵画観でないというならば、いわゆる「アカデミック」を指すものであろうか。
アカデミック派は、佐伯自身の表現によれば「淡い色彩を用いた柔らかいふわっとした画風」で一見「じょうず風」である。1920年代までは画壇の主流であり、往時の画学生は全員と言っていい程これに倣った。熊谷・東郷・佐伯皆そうである。
「自画像」(「芸大自画像」・「笠間自画像」)を描いた時期には、佐伯はアカデミック派ことに中村彝に心酔していたのである。
ヨーロッパではすでに1910年代に表現主義の画家カンディンスキーが「絵画とは外界の対象物をいかにそれらしく描くかでなく、内面の精神性を描くべきもの」と考え、抽象画に達した。具象派画家も物象の本質に迫り、あるいは精神性を表現するために「一見じょうず」風から離れようとし、それぞれ独自の画風を確立しようと工夫を凝らしていた。
佐伯も渡仏を機に、西欧諸家の画風に接してこれを遍歴し、「一見じょうず」風から脱却し、数年にして独自の画境に到達した時、早くも晩年を迎えてしまった。
「吉薗コレクション」はまさに渡仏期の作であり、若描きの(「芸大自画像」・「笠間自画像」)と比較すれば、両者の間に顕著な差異があるが、これはむしろ当然である。 鑑定人のいう天分論は、作家の生涯におけるこのような画境と画風の変化を理解していないものと思われる。
2 鑑定書理由3(青木鑑定書があげた理由3)
「吉薗・デッサン」は「被告・デッサン」をはじめとするペンや鉛筆による自画像に形似した鉛筆のデッサンである。このデッサンは対象の存在を示す光を全然とらえていない。光の存在を意識していない。だから陰影も示されていない。光を陰によって対象の形と立体感を捉えるのは絵画の基礎である。「吉薗・デッサン」は佐伯の自画像の単なる輪郭模写である。決して画家の作品ではない。
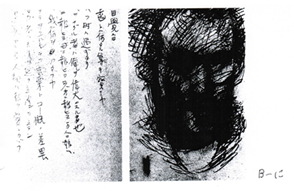

吉薗・スケッチ(被告はデッサンと称す) 被告・デッサン1
[反論]
「 吉薗・自画像スケッチ」(被告の称は「デッサン」)
吉薗・自画像スケッチ」(被告の称は「デッサン」)
はデッサンでなくスケッチである。両者について厳
密な定義はないが、作者の意図において差異があ
ることは明らかで、スケッチが対象の迅速な描写に
よる臨場的習作であるのに対し、デッサンは単色の
線によって物の形、明暗などを描いた素描で、次の
製作に進むための下絵とされる。いずれにせよ、画
家にとって絵画表現は自由なもので、光の存在を
意識しようとしまいと、それは画家の思想とその時の
心境次第である。
鑑定人の言に従えば前記熊谷・東郷両人とも画家では
ないことになる。 被告・デッサン2
また鑑定人は「吉薗・自画像スケッチ」(被告の称は「デッサン」)を「佐伯の自画像の輪郭模写」と断ずる。模写ならその模写対象がいかなる佐伯自画像なのかを明確にしていない。
そもそも陰影による立体感の表現のごときは絵画表現としては初歩のものであって、素人が模写を企てたとしても、わざわざ陰影を省かねばならない理由はない。仮に「吉薗・自画像スケッチ」(被告の称は「デッサン」)が模写だとしたら、たとい素人であっても輪郭のみならず陰影をも含めて模写する筈である。
「吉薗・自画像スケッチ」(被告の称は「デッサン」)に陰影がないのは、作家の作意と見るべきである。つまり、「吉薗・自画像スケッチ」(被告の称は「デッサン」)はいかなる自画像の模写ではなく、従って専門画家の制作にかかるものでないと断定する根拠は全くない。
3 鑑定書理由4 (青木鑑定書が挙げた理由4)
「吉薗グループ」は制作年を示されていないが、「吉薗・靴職人」は佐伯の「靴屋」(1927年作、大阪市立近代美術館建設準備室蔵)を源泉とする鉛筆の模写である。靴屋の職人がいる空間と動きは写されていない。
「吉薗・オプセルヴァトワール附近」は佐伯の「匿名・オプセルヴァトワール附近」(1927年作)の模写である。前後の建築物の関係は不明確である。
「吉薗グループ」の模写は何の目的があって作られたかは不明であるが、「吉薗グループ」の作家は模写すらできない「へたなしろうと」作家であって佐伯祐三ではない。なお、佐伯の「朝日・チンザーノの看板のある壁)」は雑誌「三彩」1991年4月号にはじめて発表されたものであり、「吉薗・チンザノの絵看板のある街角」の上限を誰にでも考えさせる作品である。

 吉薗・靴職人 (「手ガヤヒ」のメモ)
大阪市役所蔵「山発・靴屋」
吉薗・靴職人 (「手ガヤヒ」のメモ)
大阪市役所蔵「山発・靴屋」

 吉薗・オプセルヴァトワーズ附近 匿名・オプセルヴァトワーズ附近
吉薗・オプセルヴァトワーズ附近 匿名・オプセルヴァトワーズ附近
 吉薗・チンザノの絵看板のある街角 朝日・チンザーノの看板のある壁
吉薗・チンザノの絵看板のある街角 朝日・チンザーノの看板のある壁
朝日晃「佐伯祐三のパリ」所収
[反論]
本項は2段に分かれる。第1段では「吉薗・靴職人」、「吉薗・オプセルヴァトワーズ附近」、「吉薗・チンザノの絵看板のある街角」の3点が、それぞれが対応する公開作品の模写と断定する。以下、佐伯米子の加筆がなされたと見られる作品を「加筆グループ」としたうえ、「山発・靴屋」「匿名・オプセルヴァトワーズ附近」「朝日・チンザーノの看板のある壁」と称して、1点づつ論ずる。
(ア)「吉薗・靴職人」は「山発・靴屋」の鉛筆の模写で、空間と動きが写されていないと言う点について。
「吉薗・靴職人」はスケッチであって、通常スケッチにおいては遠近や動きを強調する必要はない。また仮にこれが模写ならば,模写の通念通り、たとい素人模写でも遠近法くらいは取り入れた筈である。
手本の特徴を最大限に取り入れるのが模写作業であるが、「山発・靴屋」の最も留意すべき特徴を無視した「吉薗・靴職人」は、常識から言って「山発・靴屋」の模写品とは見えない。
実際は「吉薗・靴職人」は佐伯自筆「靴職人」の原初のスケッチである。その証拠は、このスケッチに書き込まれた「手ガヤヒ」(手が良い)とある佐伯の筆跡で、これは佐伯が下描き制作上忘れてはならない重要事項を自らメモしたものである。
そもそもスケッチについても作家独特の考えがあり、佐伯はこの段階では空間や動きを強調する必要は乏しいと考えたものと思われる。故に陰影の省略を理由に、スケッチ「吉薗・靴職人」を「山発・靴屋」の模写と断定したのは完全な誤りである。
そればかりか、模写説が皮肉にも本末を転倒しているのは「山発・靴屋」が実際米子による加筆品で、その下敷きになった原画が佐伯自筆の「靴職人」の油彩下描きであり、その基になった原初のスケッチこそ、まさにこの「吉薗・靴職人」であったからである。
これには1927~8年ころの、佐伯の制作過程を認識しなければならない。
当時の佐伯は、①最初は鉛筆でスケッチし、②次に色彩を記憶する水彩で描き(これを省いてスケッチに色彩をメモしておく例もある)、③さらに、炭酸カルシウムを塗った薄手の画布にさっと油彩で下描きをし、④それを基にして最後に酸化亜鉛の厚い画布を用いたいわゆる「本画」を製作するという3~4段階であった。このことを明確に記したメモや日誌は数多く残っており、たとえば匠秀夫著『未完佐伯祐三の「巴里日記」』にその引用がある。(甲第18号証)
(イ) 鑑定人は「吉薗・オプセルヴァトワーズ附近」は、建築物の構造とその位置関
係が写されていないからなのか、写されていないがなのか、文意を明確にしないまま、佐伯の「匿名・オプセルヴァトワーズ附近」の模写と断定する。
しかし模写なら、たとえ素人の作でも、もっと「匿名・オプセルヴァトワーズ附近」に似せて描くのが常である。この場合も、鑑定人は前記「吉薗・靴職人」と軌を一にする誤りを犯しているのだが、(ア)とは異なり、本末転倒とまでは言いがたい。なぜなら「吉薗・オプセルヴァトワーズ附近」の基になったものは確かに「匿名・オプセルヴァトワーズ附近」の原画たる油彩下描きだったからである。(尚本画とは佐伯独特の用語で、特定テーマの制作過程の究極にある作品のことである。)
しかしながら、米子が加筆に線などを加えて遠近感を強調したことで、「匿名・オプセルヴァトワーズ附近」は原画の画風を失ってしまっている。いかなる意味においても「吉薗・オプセルヴァトワーズ附近」は「匿名・オプセルヴァトワーズ附近」の模写というに当らないのである。
(ウ) 鑑定人は「吉薗・チンザノの絵看板のある街角」を「朝日・チンザーノの看板のある壁」の模写と断ずる。前後の建築物の関係が不明確なことを、この断定とどのような関係を存するのか明らかにしないまま、記している。
両作品の関係は前記(イ)の「吉薗・オプセルヴァトワーズ附近」と「匿名・オプセルヴァトワーズ附近」の関係と全く同じで、ゆえに誤断も全く同じである。
第2段では、「朝日・チンザーノの看板のある壁」が雑誌に始めて発表されたのが1991年4月号であるから、「吉薗・チンザノの絵看板のある街角」の制作年をそれ以後とする。
鑑定人の論旨は「吉薗・チンザノの絵看板のある街角」と断定できるから、その制作時期は模写対象の発表時期である1991年より必ず遅い、と断じるのである。だが、「吉薗・チンザノの絵看板のある街角」の制作時期が1991年以後といえば、本件鑑定時には未だ十年経つか経たぬかという時期になる。油彩の場合、これでは新画同然であるから、原物に即して調べたら、新作なら新作と立証する手段が容易に見つかるのではなかろうか。鑑定書にはそのような記載はない。
第6 理由(2)に対する反論
鑑定書理由のうち②がこれに該当する。
鑑定書理由2
裁判所での開梱時に「吉薗・オプセルヴァトワーズ附近」「吉薗・チンザノの絵看板のある街角」は油彩特有の臭気があった。乾性油の匂いであろう。制作時(1924~28年)から70年余りして尚、臭気を発する油彩画は存在しないと思われる。また絵具層には弾力性が残っていて、この2点から「吉薗グループ」の制作は近年のものと思われた。
絵画は視覚の喜びにこたえる芸術であるが、匂いや弾力は早くに失われる。
[反論]
本項は2段に分かれる。
第1段は「臭気」で、鑑定人は特有の匂いとは何かを明らかにせず、「乾性油の匂いであろう」とのみ言っている。
宮田報告書はやや詳しく「・・・・・主に乾性油に由来する臭気と思われた。試料片最上層には油性の層が存在した。この油性の層が画面全体に塗付されていたため、臭気の主たる発生源となったものと推定している」とある。
問題はその臭気を発する物質である。鑑定人も鑑定補助者も「油彩特有の匂い」と言うから、臭気源は油彩画を一般的に構成している油性物質の一種と断定したことになる。
それでは、それは一体何なのか。本件鑑定にとって極めて重要な物質的要素であるのに、何らの科学的分析も行われていない。油性物質の成分を特定しないで「油彩画特有」と断定するのは論理性に欠けるが、更に納得しがたいのは、そこから一挙に「制作時(1924~28年)から70年あまりして尚臭気を発する油彩画は存在しないと思われる」と結論する論理構造である。何の臭気なのかを特定していないのに、70年で消えるなどとは一概に言えない。
宮田報告書は前記のように、臭気発生源を「油性物質が画面全体に塗付されてできた油性層」と推定している。
臭いだけで正体のわからない油性物質について、考えうるものがないではない。
いわゆる「色あげ」という作業である。古くなった絵画の色を良く見せるために、絵の表面に油を塗って輝きを出させるのである。今はあまり行われないようだが、以前は古い絵を売りに出す前によく行なわれていたという。
色あげにはテレピン油やリンシード油が使われることが多いが、テレピン油は後で蒸発する性質なので、本件の場合、保管中に色あげが行われたとしたら、リンシード油が使われた可能性の方が強いと思われる。
また、佐伯は、本画の画布には絵を描く前に膠を引いており、これが経年変化して絵具層に侵入しているものもある。さらに、制作中の塗りそこないを佐伯自身が修正する過程で、淡黄色の膠を広い部分まで塗広げたと推定される作品もある。
本件の問題は、色あげに使われた油や膠の臭いが、保管状態の如何に応じて、それぞれ何年経過したら、どのように変化するのか、消えてしまうのかということを精査することで解決されるのかもしれない。
鑑定人が臭気源や経年性、色あげの存無について何らの検証もしないで、70年以内に消えると断じたのは、杜撰である。
第2段では、「絵具層の弾力性」をあげる。
宮田報告書には「・・・・・吉薗・オプセルヴァトワーズ附近」「吉薗・チンザノの絵看板のある街角」「吉薗・冬景色」の画面側から採取した試料片は、感触が、明らかに、これまでの一般的な事例と異なった。採取時にメスで突くとメスの先端が絵具層に埋まり込むようで、作品の画面は、比較的柔軟な塗膜を形成していた・・・・」とあり、鑑定人はこれを受けて「吉薗グループ」を近年作と断言する。
宮田報告書中のメスの先が地塗り層に達していたのか、いないのか、達していたとして地塗り層の底には届いていたのか、どのような状況下での感触かがいま一つはっきりしない。又第1段に記した色上げがほどこされていたとすれば、その油が絵具層に浸透して、その結果弾力が増すことも考えられる。
絵具の色により弾力、硬化に変化があるものである。
感触で得られる弾力の存無、程度よりも、絵具の硬化度を科学的に調査する方が経年性の調査には必要と思われるが、そのような分析は行われていない。鑑定人の結論の導き方はいかにも偏頗、性急である。
第7 理由(3)に対する反論
鑑定書理由のうち5がこれに該当する。
鑑定書理由5
宮田報告書によれば、地塗り塗料については佐伯作品42点と今回の「吉薗グループ」3点との共通点は極めて少ないと判断される。
また、「吉薗・冬景色」に使用されたチタン白は1940年代以後の量産品であるという、佐伯の存世中にはなかった顔料なのである。
[反論]
本項は2段に分かれる。
第1段は地塗り塗料の比較である。
宮田報告書によれば、「吉薗グループ」の3点は
「吉薗・オプセルヴァトワーズ附近」
地塗り層は亜鉛華の厚い一層塗り。メディウムはエマルジョン。絵具層との境界に膠を引く。最上層は褐色を帯び透明な層が存在する。
「吉薗・チンザノの絵看板のある街角」
ほぼ「吉薗・オプセルヴァトワーズ附近」に同じ
「吉薗・冬景色」
地塗り層は胡粉。メディウムはエマルジョン。
絵具層はチタン白(ルチル型)が主成分顔料。
「笠間自画像」
地塗り層は胡粉の一層塗り。メディムは水性。
第3「本件鑑定の枠」で述べた通り、創形美術学校修復研究所が先になした佐伯品42点の地塗り層の分析結果との比較は、本鑑定では本来使用しえない性格のものであるが、鑑定人が自らの結論を導くにあたって、この比較を最重要視しているという事実を無視して反論を進めるのも空虚なことである。遺憾ながら鑑定人のイレギュラーに目をつぶらざるを得ない。
公開作品42点(第5 理由(1)に対する反論のなかで使用した例に倣い、これらの作品群はいずれも米子の加筆がなされたと見られるので「加筆グループ」と称する)の大半の35点が白亜の一層塗りで、亜鉛華を塗ったものは1点のみ、「吉薗・オプセルヴァトワーズ附近」「吉薗・チンザノの絵看板のある街角」に比して塗が薄い。胡粉のみを地塗り層とする作品はなく、胡粉と鉛白の混合塗りのものが3点ある。
「加筆グループ」は大阪市所蔵の公開作品であるが、大多数が白亜の一層塗りなのである。これにより鑑定人は「吉薗グループ」と「若描きグループ」および「加筆グループ」は、画布の地塗りにおいてまさに隔絶しているというのである。
原告代理人も事実としてそれを認める。佐伯は晩年いわゆる本画を、亜鉛華を厚く下塗りした画布に描いたのは厳然たる事実で、それが今回はしなくも「吉薗・オプセルヴァトワーズ附近」「吉薗・チンザノの絵看板のある街角」について確認されたと考える。
そして「吉薗・冬景色」が胡粉(炭酸カルシウム)の下塗りであるのは、油彩の下描き用の画布だったからであって、おそらく地塗りも薄いものと推定する。
これに対して公開作品のなかでも大阪市所蔵品は山本発次郎の蒐集品を引き継いだもので、これは米子が帰国後、佐伯のパトロンであった原告の父吉薗周蔵に請うて夫の遺作を貰い受けたが、その際与えられたのはいわゆる本画でなく、油彩下描きの方であり、これに米子が加筆して仕上げた作品を鋭意蒐集したのが発次郎であったから、「吉薗コレクション」、「加筆グループ」両グループの下塗り材料が、所論のごとく相違することがきわめて自然なのである。なお、「笠間自画像」については、佐伯が画業を完成していない画学生時代の作品であるから、胡粉を下塗りに用いた画布を使っているのが却って自然である。
「吉薗グループ」、「加筆グループ」両グループの画布の地塗りの隔絶から、鑑定人は「吉薗グループ」の作品を佐伯作品でないとするが、この論理の乱暴さを以下明確にしてみる。
ここで鑑定人が添付し且つ寄りかかっている感のある歌田所見にも触れざるを得ない。(この所見が鑑定書類に含まれるべきでないことは前述の通りであるが、鑑定人が引用しているから触れざるをえなくなる。大変不愉快なことである。)
同所見は「佐伯祐三の画布(手製)について」として数項を設けるが、要旨は次の通りである。
「佐伯が手製の画布に描いたことは広く知られ、阪本勝や鈴木誠の著書や記事から親友の証言として固く信じられてきたが、これらの伝聞と全く異なる分析結果がある。阪本によれば、膠汁にアマニ油(リンシード油)、石けん水を適量に混入し、十分にかき混ぜてから、酸化亜鉛を入れる。こうして佐伯が作った画布は、メディウムはアマニ油のエマルジョン、白色顔料は亜鉛華を使用したことになる。
ところが創形美術学校修復研究所の調査結果によると、佐伯の第1次、第2次渡仏時代を通じて地塗顔料はすべて白亜であり、亜鉛華の使用は2点にすぎず、単独使用は1点だけである。ゆえに、「吉薗グループ」の作品は「加筆グループ」とは共通点が少ないと判断した」
その判断はその通りである。ただし、問題は共通点がないこと、具体的には「加筆グループ」が佐伯の画布ならば使用している筈の亜鉛華を使っていない理由を考究することが、ここでは最も肝要である。なぜなら、佐伯の画布については、坂本・鈴木のほかにも、第1次渡仏期にパリで佐伯と親交のあった画家渡辺浩三が、佐伯が当時用いていた画布について、亜鉛華の使用を特記しているのに関わらず、なぜ「加筆グループ」の調査結果ではそれが出てこないのかを、何をさておいても究明しなければならないからである。
歌田所見は画家の秘密性を述べ、佐伯が親友を欺いたことを暗示する。一方、宮田鑑定補助者は同じ点につき「創形美術学校修復研究所調査結果」において「佐伯が亜鉛華と思い込んでいた物質は実は白亜であった」と言う。
自説と違うと、勝手にヴイヨンにしたり、画家が命の次に大事な顔料を間違うような馬鹿にしたりする。許されざる行為というほかない。
佐伯はいわゆる本画の画布に亜鉛華を厚く塗った。それが「吉薗グループ」のうち「吉薗・オプセルヴァトワーズ附近」「吉薗・チンザノの絵看板のある街角」である。
これに対し「吉薗・冬景色」は油彩下描きであるから、炭酸カルシウム(胡粉)を用いているのである。白亜と胡粉は同じ炭酸カルシウムでも、原料は異なるが、佐伯は下描き用の画布に塗るのに時期によって、両方を用いたものであろう。「加筆グループ」が油彩下描きに米子が加筆したものであることは先に述べた。
第2段はチタニウム・ホワイトに関する所論である。
「吉薗・冬景色」の絵具層に使用されている酸化チタンはルチル型であって、1940年代から量産されたもので、佐伯の時代には誕生していなかったと断言する。
量産に先立ちパリの画界で試験的にこの型のものが使われていたと推論することが出来る。佐伯の時代になかったとは言えない。佐伯がこの顔料をパリの画材店で買ったと信じるのは、佐伯自筆の「黒い革の巴里日記」に顔料の名を列挙したページがあり、その中に「ブラン・ド・チタン」の名を記しているからである。(甲第18号証匠秀夫著『未完佐伯祐三の「巴里日記」』)
当時のパリの画材店で新製品としてルチル型のブラン・ド・チタンを売っていたのではなかろうか。
第8 本件鑑定の限界
本件鑑定は「吉薗グループ」と「若描きグループ」の異同を調べるために行われた。鑑定人の犯したルール違反のために「加筆グループ」と「吉薗グループ」の異同も不可避的に明らかになった。
結果は、「吉薗グループ」は「若描きグループ」・「加筆グループ」の両方と描き方、地塗りの仕方ともに似ていないというものであった。佐伯自身の変化、本画と下描き(下描きは米子の強い個性により変えられている)の違いを考えれば当然の帰結と言うべきであろう。
鑑定人は似ていないということを超えて、[「吉薗グループ」と「若描きグループ」とは別人の制作であり、「吉薗グループ」の作者は佐伯祐三でない]と結論している。
本画である「吉薗・オプセルヴァトワール」「吉薗・チンザノの絵看板のある街角」を、米子が加筆した「匿名・オプセルヴァトワーズ」と「朝日・チンザーノの看板のある壁」の複写として比較し、前者を複写とも言えない下手な模写と酷評する。「吉薗自画像」の場合は更に珍妙である。輪郭複写と言いながら模写された対象を明示せず、陰影がないから素人の下手な作であるという。暴論ここに極まれりの感がする。その理由は前述した。
佐伯の地塗りの材料について歌田は佐伯が友人にウソをついたと考え、鑑定補助者の宮田順一氏は己の調査結果との違いを「佐伯が亜鉛華と白亜を間違いつづけた」と言うことにして解決している。安易と言うも愚かである。
本件鑑定で客観的に明らかになったことは、「吉薗グループ」と「若描きグループ」との間には相違点が多く存在するということである。渡仏時期の作品と周作時代の作品とを、描き方を目視により、地塗り材料を科学的分析により比較調査して、観史類似点が多いとすれば奇異なことである。
鑑定人は2年弱の時間をかけて本件鑑定を行っているのだが、1頁の鑑定理由で結論に至っている。短い理由の中には上手な文学的表現も見られるが、1~5の各理由の関係等を説明することもなく結論を急いでいる。その理由が首肯しえないものであることは述べた通りであるが、歌田所見なる許されない加勢を依頼する鑑定人の用心深さとは裏腹に、推理の方法、論の展開はいかにも粗雑である。[「吉薗グループ」と「若描きグループ」は似ていない]これ以上でもこれ以下でもない。本件鑑定から恣意と専断を除けば、残る結論はこれだけである。このことが明らかにされた限度で本件鑑定を評価する。
第9 本件訴訟における本件鑑定の位置付け
本件の訴えは「被告中島がその著書のなかで吉薗コレクションを贋作と決めつけ、被告二見書房はそれを了として出版発行し、両社共同して不法行為をなし、原告の名誉を害した」というものである。
テレビの人気番組の看板鑑定人として名のあがった被告中島が「ものを買うときは、耳で買わない、目で買え」と説いている一文の中で吉薗コレクションを贋作ときめつけている。
被告中島は焼物を専門とする人で、洋画に関しては素人に近い存在であるにもかかわらず、実物を全く見ずに、或いは写真すら見ずに(平成10年12月21日付原告準備書面)「遠野あたりに佐伯作品が大量にあるわけがない」と言う理由にもならぬ理由で贋作としている。
被告らの行為が外形上名誉を毀損するものであることは明白であり、「吉薗コレクションが贋作であることが完全に立証された場合」その行為の違法性が阻却されるのであろう。
本件鑑定は結論で吉薗コレクションを贋作としているが、結論を導いている各理由が根拠に乏しいことは第1~第8で述べた通りである。贋作であることの立証に成功しているとは到底言えない。以上。
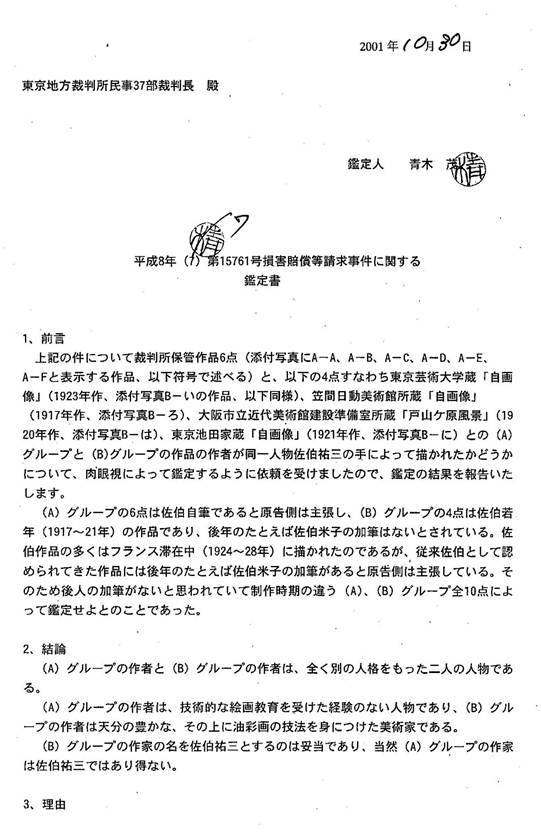 Ⅲ・青木茂鑑定書(全2枚)
Ⅲ・青木茂鑑定書(全2枚)